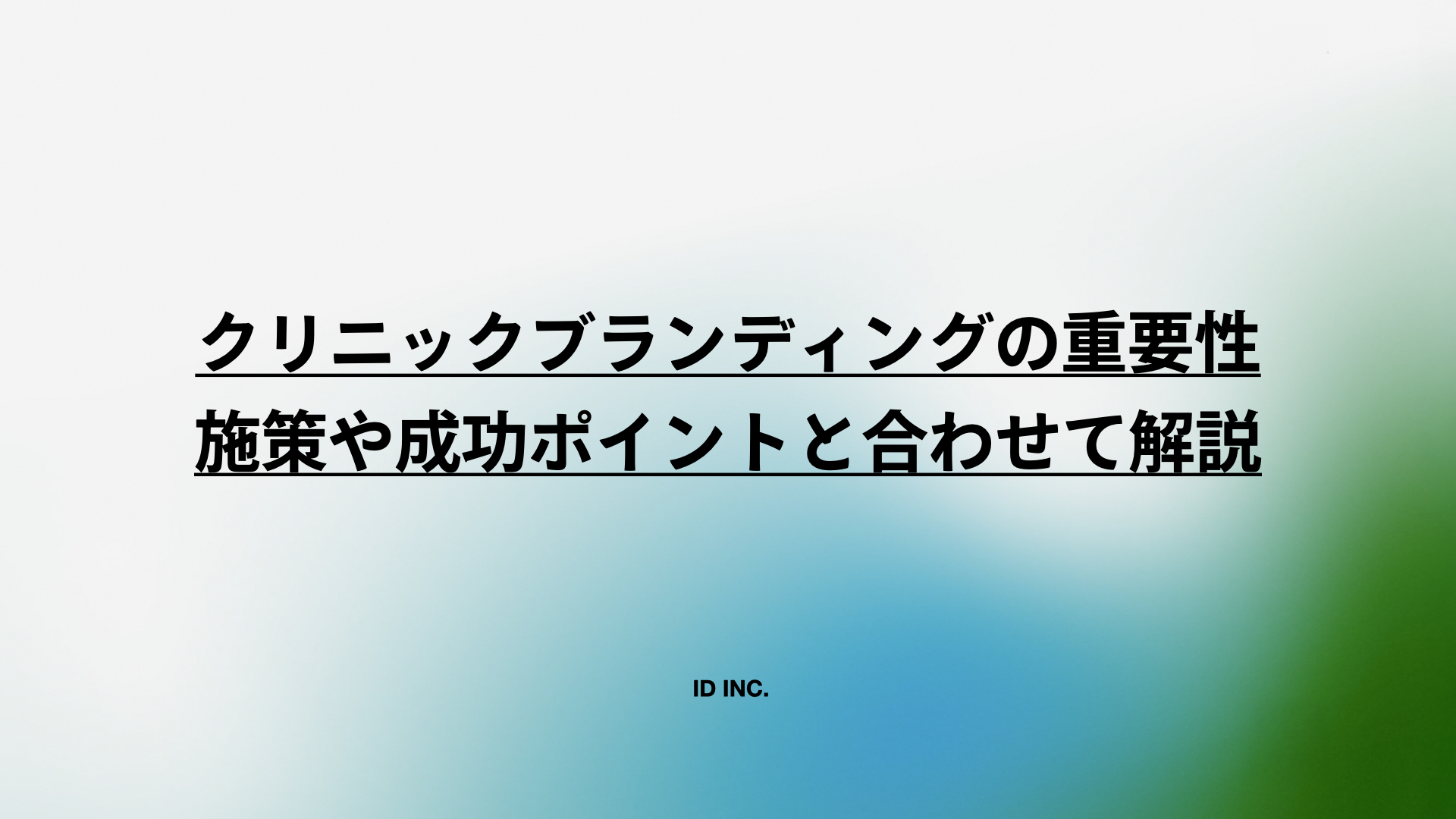ブランディングとは?おすすめの会社や構成要素と合わせて解説
Branding
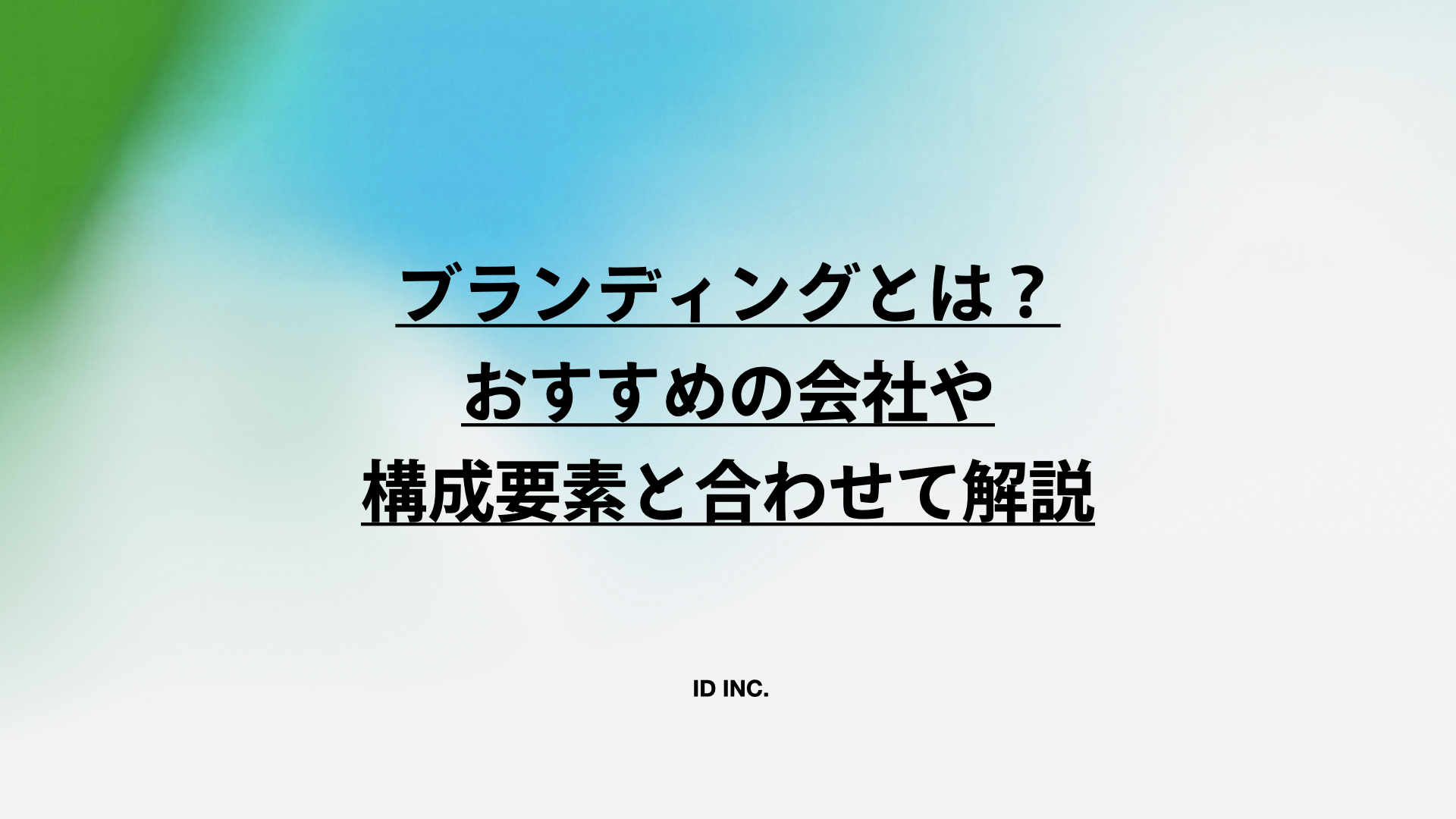
地方の中小製造業において、信頼を獲得し受注を増やすためには、従来のロゴやコーポレートサイトだけでは十分な競争力を維持できません。今日の市場では「企業の強み」や「ブランドの一貫性」を明確にし、顧客や取引先の記憶に残る体験を生み出すことが求められています。
ブランディングは単なるデザイン刷新ではなく、企業の理念や価値観を可視化し、社内外に一貫したメッセージを届けるプロセスです。その結果、営業資料や展示会、海外取引など、あらゆる顧客接点で信頼と選ばれる理由を生み出すことができます。
本記事では、ブランディングの基本概念とその種類、デザインの構成要素、おすすめの会社について体系的に解説します。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。
東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください
この記事で分かること
ブランディングとは
地方の中小製造業にとって、「ブランディング」は経営の成長戦略の一つとして注目されています。しかし、ロゴやデザインだけがブランディングと誤解されやすいのが現状です。
実際にはブランドとは「消費者の心の中にある企業やサービスへのイメージ」を意味し、信頼感や共感を獲得するための総合的な活動を指します。
ここでは、ブランディングの種類について以下の4点を解説します。
では、なぜこのように多角的なアプローチが求められるのでしょうか。
その理由は以下の3点です。
- 市場での信頼性の向上: 展示会や海外取引では、取引先や新規顧客が企業のWebサイトやカタログ、ロゴなど「見た目」から第一印象を持ちます。見た目に時代とのずれがある・統一感がない場合、「本当に信頼できる会社なのか?」という不安につながりやすくなります。
- 差別化による受注増: 消費者は無意識にブランドを比較し、メリットや安心感、独自の価値に惹かれて選択します。どの企業も同じような言葉やデザインでは、「選ばれる理由」にはなりません。だからこそ、強みや価値観を明確に言語化し、一貫したブランディングが必要となります。
- 内部浸透による組織強化: 理念やミッションが形骸化し、社員に浸透しないと「一体感」が生まれません。特に代替わりや組織の拡大、採用活動強化時には「何を大切にしている会社なのか?」を言語化し、社内外に明確に伝えることが不可欠です。
以上のように、ブランディングは外部への信頼だけでなく、差別化や組織力強化にも直結します。
では実際に取り組む際、どのような手法があるのでしょうか?
ブランディングの具体的なアプローチは、目的や課題に応じて大きく4つの種類に分かれます。
それぞれを順に解説していきます。
① 企業ブランディング
企業ブランディングは、会社全体のイメージや価値観、存在意義を明確にし、社外・社内に発信していく戦略です。特に中小製造業においては、受注拡大や新規市場開拓、優秀な人材確保を目指す上で「どんな会社なのか」を分かりやすく伝えることが成長の鍵となります。
このブランディングの主なポイントは以下の3つです。
まず、企業の「ミッション」「ビジョン」「バリュー」を明確にし、トップの想いや将来像を全社員で共有できる形にまとめます。これにより、経営陣の交代や事業継承の場面でも「会社のらしさ」がぶれずに継続されます。
次に、ロゴや名刺、パンフレット、Webサイトなど「見た目」の統一と、外部から見た時の安心感や信頼感を高めることが求められます。ロゴやWebサイトを刷新することで、展示会や海外パートナーにもしっかりとアピールできるでしょう。
さらに、創業ストーリーや経営理念など「背景」を伝えることで、他社との差別化や共感の獲得に直結します。顧客や取引先はもちろん、社員やその家族、地域社会まで幅広く好印象を与える効果が期待できます。
企業ブランディングでは、これらの要素を一貫して整理し、社内外で「同じメッセージ」を伝える仕組みを作ることが重要です。
ただし、単にスローガンやロゴを新しくするだけでは効果は限定的です。全社員を巻き込んだ議論や方針策定が「浸透」と「成果」につながります。
行動に移す際は、経営陣や現場リーダーを中心に小さなチームでミッション・ストーリーを言語化し、段階的に社内外へ展開していきましょう。
② 商品・サービスブランディング
商品・サービスブランディングは、個々の製品やサービスに対して「独自の価値」や「個性」を明確に打ち出すアプローチです。企業全体のブランディングと異なり、特定の製品ラインや新サービス、既存商品のリニューアル時に特に重視されます。
このブランディングが重要な理由は以下の3点です。
まず、商品やサービスには「機能」や「性能」だけでなく、そのブランドならではの「らしさ」が求められます。そしてこの「らしさ」とは、たとえば品質へのこだわりや独自の世界観、あるいは特定のターゲット層に向けたメッセージなど、多様な要素によって形づくられます。
消費者が数ある選択肢の中から自社商品を選ぶ理由は、価格や性能以上に「このブランドなら安心」「自分に合っている」と感じられるかどうかに左右されるのです。
次に、競合他社との違いを明確化することも大切です。似たような製品が並ぶ展示会やカタログでは、「独自のネーミング」や「印象的なパッケージ」「心に残るキャッチコピー」が選ばれる決め手となります。
また、商品ごとにSNSでの発信やキャンペーンを分けて展開することで、ファン層を拡大しやすくなります。そして、商品ブランディングでは社内外の一貫性も不可欠です。製品カタログ、取扱説明書、営業資料、Webサイト、さらにはカスタマーサポートまで、統一感のあるデザインや表現を用いることで、顧客の「期待」と「満足度」が大きく向上します。
注意点として、製品ごとのブランドを独立させすぎると、企業全体のブランドイメージと分離しがちです。全体ブランド方針と連携しながら商品独自の「個性」を引き出すことが、中小企業にとっても持続的な強みになります。
新商品開発やサービスリニューアルの際には、「市場で選ばれる理由」と「自社ブランドらしさ」の両方を明確に言語化し、実際のデザイン・販促に落とし込むプロセスを意識してみてください。
③ 採用ブランディング
採用ブランディングとは、「この会社で働きたい」と思われる魅力を明確に打ち出し、求職者から選ばれるためのブランドづくりを指します。地方の中小企業では「良い人材が集まらない」「応募があっても自社の強みが伝わらない」といった悩みが多い中、採用ブランディングは今や採用力強化の必須戦略となっています。
採用ブランディングで押さえるべきポイントは以下の3つです。
まず、求職者が自社を知るきっかけはコーポレートサイトや求人媒体、SNS、さらには社員やOB・OGからの口コミなど多岐にわたります。情報が整理されていなかったり、魅力がうまく言語化できていなかったりすると、優秀な人材は他社へ流れてしまいます。
そこで自社ならではの価値観、仕事のやりがい、キャリアパスや福利厚生の特色などをしっかり「言葉」にして伝えることが重要です。
また、現場社員のリアルな声や働き方、社内イベントの雰囲気をSNSやオウンドメディア、会社案内動画などで発信すると、「実際にどんな会社なのか?」がより伝わります。これにより、単なる待遇や条件だけでなく、共感や愛着を持つ求職者を引き寄せられます。
さらに、採用ページや募集要項、パンフレット、エントリーフォームなどのビジュアルも一貫したデザインに刷新しましょう。ロゴやブランドカラーが統一されていないと、「どこか古い」「信頼できるのか?」という印象を与えてしまいがちです。
特に、製造業では現場の雰囲気や製品への誇り、社内の成長機会など「らしさ」を分かりやすく伝えることで、他社との差別化が実現できます。
注意したいのは「見せかけ」や「盛りすぎた演出」を避けることです。実態と乖離したメッセージは早期離職や社内不信につながるため、正直かつリアルな情報発信を心がけましょう。
採用活動がうまくいかない時ほど、自社の魅力再発見から取り組みを始めてみてください。
④ インナーブランディング
インナーブランディングは、従業員一人ひとりに「自社の理念やブランド方針、価値観」を浸透させ、社内での一体感や誇りを高めるための活動です。外向きの発信だけでなく、「中から強い会社」をつくるための根幹とも言えるブランディングです。
この分野で重視すべきポイントは次の3点です。
まず、インナーブランディングの起点となるのは「ブランド方針の明確化」です。ビジョンやミッション、バリューを分かりやすく整理し、全社員に伝わる言葉でまとめます。これはトップダウンで一方的に伝えるのではなく、現場も巻き込みながら共感できる内容に仕上げることが大切です。
次に、浸透を促すための仕組みづくりです。たとえば定期的な全社ミーティングやラーニングコンテンツの整備、ミッション・バリューを掲示するポスター、ブランドブックの配布など、様々な方法で社員の目や耳に触れる場面を増やします。
また、「理念は毎年見直すもの」「一度決めて終わりではなく、育て続けるもの」というスタンスで、定期的なアップデートや振り返りを必ず行いましょう。
さらに、ブランドの「らしさ」や強みを社員全体で共有できるブランドムービーや、社内報などのビジュアルコンテンツも有効です。単なる文章だけでなく、ストーリーや事例を交えて伝えることで、自分ごととして理解されやすくなります。
注意したいのは、インナーブランディングが「形骸化」しやすい点です。経営陣だけが理解していても、現場の社員まで伝わっていなければ意味がありません。「なぜこの会社で働くのか」「自社はどこを目指しているのか」を全員が語れるようにすることが理想です。
中小企業では現場リーダーや管理職を巻き込んで少人数から段階的に浸透させる方法が効果的です。インナーブランディングによって、組織のまとまりや従業員満足度、ひいては離職率の低下にもつながります。
ブランディングデザインの構成要素
ブランドの第一印象や信頼感を大きく左右するのが「ブランディングデザイン」です。とくに地方中小企業のように、展示会や新規取引の場面で相手に選ばれるためには、企業ロゴやカタログ、Webサイトの見た目を一新し、プロフェッショナルな印象を与えることが重要です。
このセクションでは、ブランディングデザインを構成する以下の要素について整理します。
それぞれの要素が、どのようにブランドイメージやビジネス成果に影響を与えるのかを、具体的に解説します。また、各要素の刷新・統一がなぜ成果につながるのか、失敗を避けるためのポイントも明らかにしていきましょう。
構成要素① ロゴ

ロゴは「ブランドの顔」となる最も重要なビジュアル要素です。名刺、パンフレット、カタログ、Webサイト、看板など、ありとあらゆる顧客接点で必ず使われるため、第一印象の8割を決定づけるとも言われています。
ロゴ刷新がもたらす主な効果は次の3つです。
ロゴが時代に合っていなかったり、視認性が悪い場合、「時代遅れ」「この会社は大丈夫か?」といったマイナスイメージを持たれるリスクが高まります。逆に、シンプルで記憶に残るロゴは、名刺交換やWeb訪問、製品カタログの中でも強い印象を残し、顧客の記憶に定着します。
また、ロゴは会社やブランドの「理念」や「ビジョン」を視覚的に表現するものです。たとえば、フォントやシンボル、色使いに込められた意味が「らしさ」や強みをストレートに伝える役割を持っています。最近では、スマートフォンやSNSアイコン、Webのファビコンなど小さな表示でも判別しやすいデザインが求められるようになりました。
注意点としては、ただ「かっこいいデザイン」にするのではなく、ブランド方針や事業内容と一貫性のあるロゴにすることです。さらに、横組み・縦組み・シンボル単体など、用途に応じたバリエーションを用意することで、使い勝手と一貫性の両立を図りましょう。
構成要素② ブランドカラー

ブランドカラーは、商品やサービス、またはブランド自体の「らしさ」を象徴する色の要素です。視覚的インパクトはブランド認知の早さや印象の定着に直結し、名刺やWebサイト、パンフレットなどあらゆる顧客接点で一貫したメッセージを発信します。
ブランドカラーが果たす役割は主に3つです。
まず、色彩は人間の感情に直接働きかけるため、ロゴやWebサイトに統一されたカラーを使うことで、「信頼できそう」「先進的だ」「温かみがある」といった印象を数秒で伝えられます。たとえば、青は誠実さや安心感、赤はエネルギーや情熱、緑は安心や成長をイメージさせます。
ブランドカラーが定まっていない、もしくは媒体ごとに色が違う場合、「統一感がない」「印象に残らない」といったデメリットにつながります。
ブランドカラーを選定する際は、社内外のヒアリングやワークショップを行い、「自社の商品がどんな印象を持たれたいのか」を明確にします。ブランド方針や理念と一貫した意味付けを持たせることで、単なる「色選び」ではなく、強いブランドストーリーを作ることが可能です。
さらに、製品カラーや販促ツール、作業服など、あらゆる場面に反映しやすいカラーパレットとして定義しておくと、今後の展開でも一貫性が保てます。
注意すべきは、視認性やアクセシビリティ(誰でも見やすいか)を必ず考慮することです。コーポレートカラーを決めたら、同系色・補助色との組み合わせも決め、印刷物・Web・看板など各メディアでブレずに再現できる運用ルールを設けましょう。
ブランドカラーの刷新や新規策定の際は、必ず現状の色づかいを棚卸しし、業界のトレンドや競合調査も行いながら、自社ならではの「唯一無二の色」をぜひ追求してみてください。
構成要素③ パッケージデザイン

パッケージデザインは、製品やサービスの外装デザインやカタログ、リーフレットなど、実際に顧客の手元に届く「モノ」を通じてブランドイメージを体現する要素です。特にBtoB製造業では、展示会や営業訪問で手渡すカタログや製品パッケージが、そのまま会社の信頼感を左右します。
パッケージデザインが担う主な役割は以下の3つです。
まず、パッケージやカタログのデザインは、「単に情報を並べただけ」では効果が出ません。ブランドカラーやロゴ、統一されたフォントやビジュアルスタイルと連動させ、「自社らしい世界観」を作り込みます。
たとえば、洗練されたレイアウトや明確なアイコン、分かりやすい情報設計は、それだけで「信頼感」や「先進性」を伝え、商談時の信頼度を大きく向上させます。
また、カタログやパッケージには「ストーリー性」を盛り込むことが効果的です。製品の背景や開発コンセプト、他社と違うポイントを明快な見出しやコピーで表現することで、顧客に「ワクワク感」や「共感」を与えます。
さらに、営業現場での配布物や展示会での見せ方まで一貫して設計することで、どのタッチポイントでもブランド体験にずれが生じません。
注意点として、古いカタログや不統一なパッケージが残っていると、せっかくの新しいブランドも「ちぐはぐな印象」になります。全ての媒体で「一貫したデザイン・表現」に統一することが信頼性アップのポイントです。
構成要素④ フォント
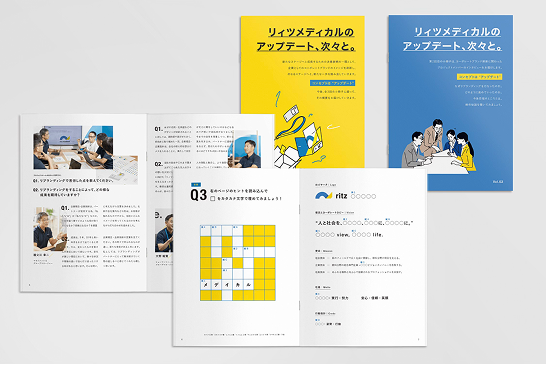
フォントは、ロゴやカタログ、Webサイト、名刺、プレゼン資料など、あらゆるビジネスコミュニケーションの中で「見えないブランドイメージ」をつくり出す要素です。見た目の印象はもちろん、読みやすさや信頼性にも直結します。
フォントが与える主な影響は次の3つです。
まず、全ての媒体でフォントを統一することで「信頼感」や「安心感」を醸成できます。たとえば、資料やWebでバラバラの書体を使っていると、「細部まで気が回らない会社」というネガティブな印象を与える原因になります。
一方、コーポレートフォントを定めて全体で活用することで、見た瞬間に「自社らしさ」が伝わります。
フォント選びは「イメージ」と「使いやすさ」のバランスが大切です。
たとえば、サンセリフ体は先進性やシンプルさ、セリフ体は伝統や信頼感、手書き風は親しみや温かみなど、それぞれ異なる印象を与えます。
また、ブランド方針や業界特性、メインターゲットにふさわしい書体を選びましょう。もちろん、日本語・英語どちらの対応も忘れずに検討する必要があります。
注意すべきポイントは、読みやすさと再現性です。
小さい文字やデジタル表示、印刷物でも可読性が高いこと、文字の崩れやレイアウトのずれが生じないことを確認してください。
また、OSやデバイスによる見え方の違い、フォントのライセンス・コストも必ず事前に調べておきましょう。フォントの一元管理には「デザインガイドライン」の整備が有効です。
使える書体やサイズ、行間、見出し・本文の使い分けなどルールを明文化し、チーム全員で共有しましょう。ブランドイメージと実務効率を両立できる運用体制をつくることが、持続的なブランド力強化の鍵です。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。
東京・神奈川でブランディング会社をお探しの方は、ID INC.の取り組みをご覧ください
おすすめのブランディング会社5選
ブランドの刷新や強化を考える際、「どの会社に相談すれば良いのか分からない」という声はとても多く聞かれます。とくに地方の中小企業では、地域にブランディング専門会社が少なく、広告代理店やデザイン事務所とどう違うのかも判断しづらいのが現実です。
ここでは、おすすめのブランディング会社5社をピックアップします。
各社の特徴や得意分野を比較し、自社の課題や目標に合ったパートナー選びの参考にしてください。
- ID株式会社
- 株式会社エイトブランディングデザイン
- 株式会社MIMIGURI
- 株式会社パーク
- グラムコ株式会社
ID株式会社

| 会社名 | ID株式会社 |
| サービス | ブランディング戦略、ロゴ開発、Web制作、カタログ・パッケージ制作、空間・サインデザイン、組織浸透支援 |
| 実績 | ・安心お宿(カプセルホテル) ・Connecting The Dots(コワーキングスペース) ・リィツメディカル(眼科医療機器商社)など |
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区 |
| 公式サイト | https://include.bz |
ID株式会社は「AI×ブランディング」を強みに、戦略立案からデザイン制作、運用までをワンストップでサポートしています。コンサルティングにとどまらず、実制作や社内浸透まで対応できるため、はじめてブランディングに取り組む企業にも安心です。
株式会社エイトブランディングデザイン

| 会社名 | 株式会社エイトブランディングデザイン |
| サービス | ブランドコンサルティング、ネーミング開発、ロゴ・VI設計、パッケージデザイン、空間設計、ブランドサイト制作 |
| 実績 | ・COEDO(ビールメーカー) ・nana’s green tea(飲食チェーン) ・ユースキン(製薬・スキンケア)など |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 公式サイト | https://www.8brandingdesign.com |
株式会社エイトブランディングデザインは、戦略とクリエイティブを両立させながら、ブランドの「芯」を明確にし強みに変えることを得意としています。独自の「フォーカスRPCD®」や「ブランディングデザインの3階層®」を用い、企画から実装まで一貫して伴走します。ブランドを長期的に育てていきたい企業におすすめです。
株式会社MIMIGURI

| 会社名 | 株式会社MIMIGURI |
| サービス | 経営コンサルティング、多角化支援、事業開発、組織設計、文化開発、人材開発、学習プラットフォーム「CULTIBASE」 |
| 実績 | ・花王(化粧品・日用品) ・カシオ計算機(精密機器) ・コクヨ(文具・家具)など |
| 所在地 | 東京都文京区 |
| 公式サイト | https://mimiguri.co.jp |
株式会社MIMIGURIは、研究機関としての理論構築と、経営現場でのファシリテーション力をあわせ持つコンサルファームです。経営者やリーダーと共に多角化や組織改革などに伴走し、学びのプラットフォーム「CULTIBASE」も提供しているので、複雑な経営課題にじっくり向き合いたい方におすすめです。
株式会社パーク
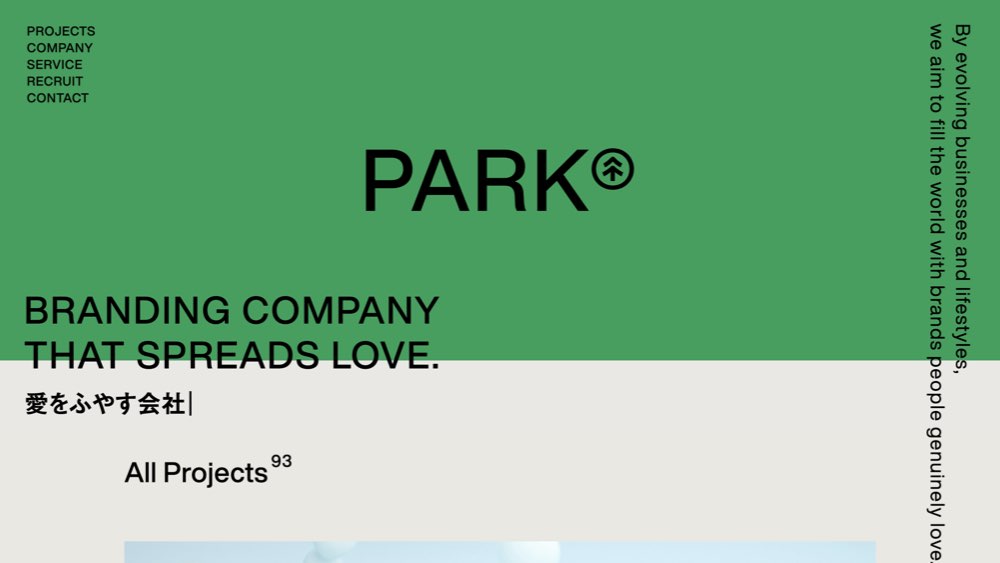
| 会社名 | 株式会社パーク |
| サービス | 公共空間開発、遊具事業、都市景観設計、サイン制作、屋外家具事業 |
| 実績 | ・東京都内公園(公共施設) ・地方自治体プロジェクト(公共事業) ・大手デベロッパー案件(都市開発)など |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 公式サイト | https://parkinc.jp |
株式会社パークは、公園や広場などの公共空間づくりを得意とする会社です。遊具やベンチ、サインなどを自社で設計・製造・施工まで一貫対応できる体制を持ち、街や地域の人々が安心して集える場所のデザインを支援しています。公園・街づくり・地域活性化のプロジェクトに携わりたい方におすすめです。
グラムコ株式会社

| 会社名 | グラムコ株式会社 |
| サービス | ブランド戦略立案、CI開発、ネーミング、パッケージデザイン、空間設計、コミュニケーション開発 |
| 実績 | ・バンダイナムコホールディングス(エンタメ) ・UACJ(金属) ・YMCA(教育・福祉)など |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 公式サイト | https://www.gramco.co.jp |
グラムコ株式会社は、日本における最古のブランディング専業ファームとして、長年蓄積されたブランド構築のノウハウを持っています。戦略立案からクリエイティブ、内部浸透やグローバル展開まで一気通貫で対応可能です。特にグローバルブランドや長期プロジェクトで、確かな信頼性を重視する方におすすめです。
まとめ
展示会や海外取引、採用強化など、選ばれる理由をつくり、経営の成長スピードを高めるためには、単なるロゴ刷新やカタログの見直しだけでは足りません。ブランドの「らしさ」や価値観を整理し、組織全体で一貫したイメージを発信することが本質です。
本記事では、ブランディングの4つの主要タイプと、ロゴ・ブランドカラー・パッケージ・フォントなどデザイン面の構成要素、おすすめのブランディング会社の比較まで網羅的に解説しました。
各社の強みをまとめていますので、「何から手をつけるべきか」「誰に相談すればよいか」迷った際は、表を活用しながら自社の優先課題に合うパートナー選びを進めてみてください。
重要なのは、「なんとなくカッコよくしたい」ではなく、「どんなブランドでありたいか」を明確にし、一貫した戦略・運用・社内外への共有を続けることです。
「行動したいが、まず何から始めるべきか」「社内で足並みを揃えたい」など、方針に迷う場合は、プロのブランディング会社や経験者に相談するのも大きな一歩です。
本記事の内容について、「自社に合わせて個別相談したい」「さらに深堀したいテーマがある」など、ご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

AI活用で理念を素早く可視化し、ブランド戦略〜CI・VI設計までワンストップで伴走します。まずは無料相談・資料請求から。